愛は現実を超え、愛は現実のただ中に―シューベルト/ゲーテ「恋人のそばに」D.162
ゲーテの詩との出会いは、シューベルトにあまりにも豊かなインスピレーションをもたらしたようだ。1814年の「糸を紡ぐグレートヒェン」D.118を皮切りに、「旅人の夜の歌」D.224、「野ばら」D.257、「きみよ知るや南の国」(ミニヨンの歌)D.321、そして「魔王」D.328などの、1815年の怒濤のような創作が続く。それらの数々の名作に並んで「恋人のそばに」D.162がある。
データ的なことをまず片付けておこう。詩はゲーテ、1795年の作だが、もとになった作品があった。フリーデリケ・ブルン Friederike Brun の「わたしはあなたを思う Ich denke dein」である。彼女の詩は「わたしはあなたを思う」から始まる5つのスタンザからなるが、ゲーテは4つに圧縮し、しかも内容を拡張した(後述)。なお1799年にベートーヴェンも同じゲーテの詩をもとに作曲している。
「恋人のそばに」は以下のとおり。
わたしはあなたを思う
ふるえる陽光が海を照らす時
わたしはあなたを思う
ほのかな月の光が泉に影を落とす時
わたしにはあなたが見える
はるかな道に砂ぼこりが舞い上がる時
深い夜に 険しい道で
旅人が身をふるわせる時
あなたの声が聞こえる
低くざわめきながら彼方で波が高まる時
静かな森の囁きにしばし耳傾け
すべてが沈黙した時
わたしはあなたのそばにいる
どんなに離れていても あなたはそばにいる!
太陽が沈み やがて星がまたたくだろう
おお あなたがここにいたなら!
もとになった詩のわたしは「思う」から、ゲーテは「見える」「聞こえる」、さらに「いる」へと拡張した。すなわち、あなたという対象は、想像から感覚、そして存在へと、わたしの全体に映し出された、大いなる「現象」となるのである。
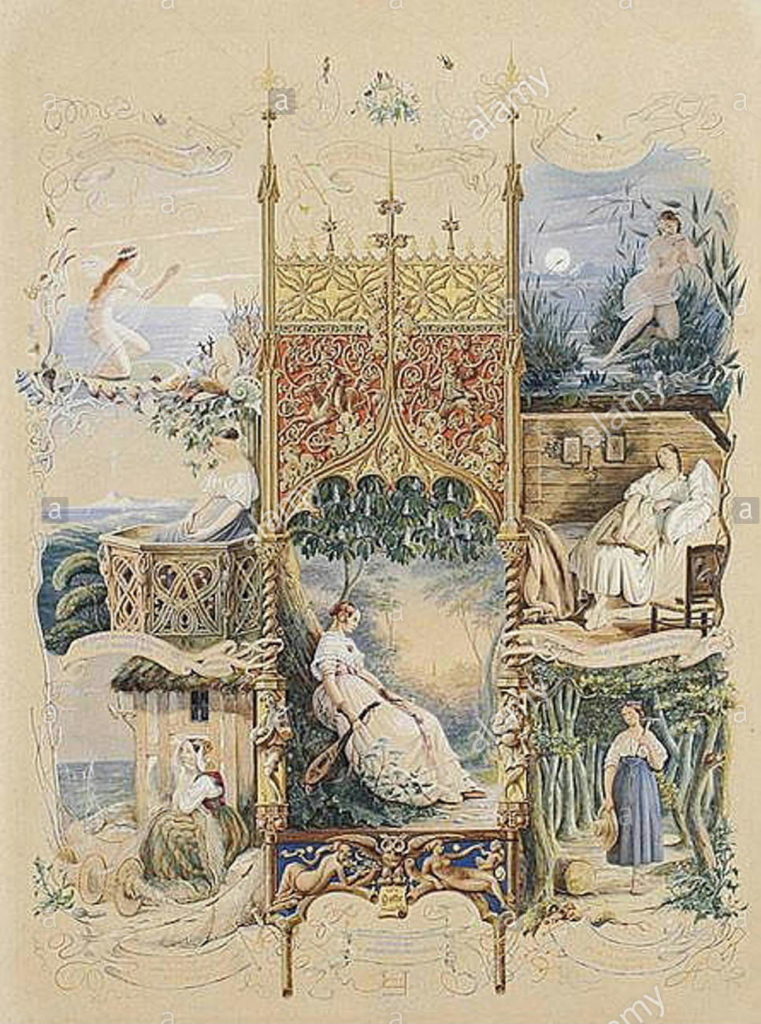
ゲーテの詩に作曲されたシューベルトの音楽は「ゆっくりと、荘厳に、優美に Langsam, feierlich, mit Anmut」と指示された。まさに荘厳な光芒射す音楽である。

八分の十二拍子、6小節の音楽を4回繰り返すだけの音楽である。いわゆる一定の旋律に歌詞が変わるという有節歌曲で、「野バラ」などと同じ、民謡的で素朴な歌に見える。そこに前奏と後奏の2小節がつく。驚くべきは前奏である。まるで『トリスタンとイゾルデ』前奏曲のように半音階的に上昇し、ハーモニック・リズムは徐々に圧縮され、音楽は高まり、切迫する。あと一滴で思いが器からこぼれ出すその瞬間に、最高音で旋律が歌い出される。そして感動が氾濫する。きわめて深いインスピレーションが結晶した音楽である。
旋律線の基本はアーチ状の弧にある。ところが「恋人のそばに」では旋律の頂点に歌い出しがあるという特異な形となった。実は、この形状は感動的な名旋律に少なくない。次の例、オペラ『蝶々夫人』の有名なアリア「ある晴れた日に」もそうである。♭6つの変ト長調という特殊な調性が共通性していることからも、プッチーニの頭のどこかに「恋人のそばに」があったのではないか、と思わせるくらいである。

「恋人のそばに」で「見える」とか「聞こえる」とかいわれているのは、文字どおりの意味ではあるまい。そもそも「深夜に」見えるとか、「森の沈黙」に聞こえる、というのはいささか怪しかった。彼女は本当に見たり、聞いたりしているのではない。これらは「それほど強くあなたのことを思っている」という詩的な表現なである。思うあまり、恋人の姿を見てしまったり、声を聞いてしまったりすることはありうる。それほどわたしは愛に深くとらわれている。主人公の「妄想」の激しさは、彼女を支配している愛の強さと真実性の証なのである。妄想は、最後には、ついに「いる」というところにまで達する。「愛は時空を超える」のである。
ところが最後の一行でどんでん返しが来る。「おお あなたがここにいたなら!」。確かなことはあなたはここに「いない」。「恋人のそばに」の第2のテーマは「愛は現実だ」ということなのである。「そばにいる」という現実こそが愛だ。
「愛は時空を超える」「愛は現実だ」……これらは矛盾であり、一見、相容れないようだ。しかしこの矛盾こそが「愛」にほかならない。離れていても、想像でき、感じることができ、存在を妄想さえできれば、それでいいというのは、愛だろうか。ゲーテがいうのは、リアルな「そばにいる」を願うのも愛だ、ということなのである。聖書に「神を愛するがごとく、汝の隣人を愛しなさい」(『マタイによる福音書』第22章37-39節)という言葉がある。神への愛は「時空を超える愛」である。隣人への愛は「現実的な愛」である。聖書のこの言葉は「二つはセット」である、ということなのである。
神へのどんな純粋な愛といえど、隣人を愛せないなら、それは愛とはいえない。ところがそれが可能であるどころか、世界にはそんな「愛」が溢れている。神を愛するといって、争いが起きている。神への愛のためにテロが起きている。神への愛は殺人を正当化しさえする。ところが「隣人」とは無差別の他者である。それは「敵」でも「味方」でもない。いやそのどちらもであるはずだ。聖書の言葉はそのすべてを愛せよというのである。「神を愛するがごとく」。ところが往々にして二つは切り離され、憎悪を生み、殺戮を繰り返す。それが人類の歴史ともいえる。
しかし「時空を超えた」=抽象的・形而上的な愛、および「愛は現実」=具体的・形而下的な愛の二つはあくまでも「ふたつでひとつ」なのである。ここに「恋人のそばに」の究極のテーマがあるといえよう。詩の大部分は抽象的な愛を歌っていたが、それだけでは空疎で、ただの妄想にすぎなかっただろう。しかし最後の一行の感情のほとばしりによって愛が完結する。抽象的な「幻影」だけではなく、あなたという「存在」を具体的に愛さなければならない。形而上的な愛と形而下的な愛は少しも矛盾することなく、それらの統合において真の愛が成就する。
シューベルトの音楽は有節形式に特徴があったが、あなたの不在を暴露する最終行のひねりは、ある種硬直したこの形式により、浮き彫りにされるのである。深い戦略性が読みとれるが、作曲者は意図したかどうか。それを考えるには補足が必要だろう。



